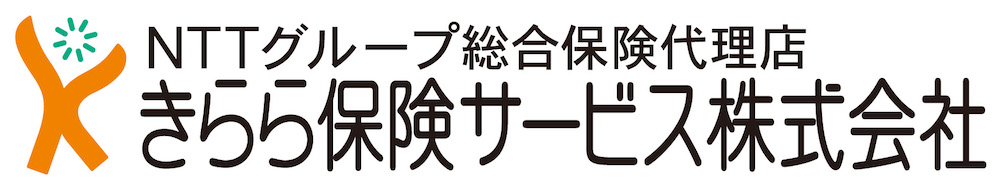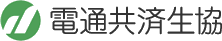Q.1 賃金を下げられました!
雇用されている社員全員が今年2度に渡って賃金を下げられました。これは最低賃金や労働条件に違反していないのでしょうか?
Answer
ご相談内容の要点は(1)労働条件(賃金)の切り下げ、(2)最低賃金の保障の適否の問題になると思います。そこでまず、 この2点の法的根拠について、触れます。
(1)雇用契約と異なる労働内容は、まず使用者(経営者)と話し合いを!
1つ目は、就業規則(賃金規定)の不利益変更による労働条件の切り下げです。就業規則の変更に際して、使用者は「手続面」で
1. 労働者の過半数を代表する人の意見を聴いたか(労働基準法〈以後、労基法〉第90条)。
2. 変更した就業規則は労働基準監督署(以後、労基署)へ届け出たか(労基法第89条)。
3. 労働者に周知したか(労基法第106条)。を確認しましょう。次に「内容面で」
4. 変更内容は法令に違反していないか(労基法第92条)。
5.不利益変更に合理性(業務の必要性)はあったか(最高裁判決)。
を確認しましょう。
2つ目は労働契約(就業規則によらない場合)の不利益変更による労働条件の切り下げです。労働契約の変更に際して使用者が、
1. 労働者の個別同意を得ているか(裁判例)。
2. 変更内容は法令に違反していないか(労基法第14条、労働組合法16条)。
を確認しましょう。
Q.2 異動命令は受けざるを得ない?
異動命令が出たのですが、同じ企業グループでも法人が違うので、一度退職して別企業に採用される――といった形です。年金制度や待遇も変わり、私にとって不利益を感じます。このようなことは、法律違反にはならないのでしょうか。また、異動命令は受けざるを得ないのでしょうか?
Answer
ご相談にある異動命令は転籍出向に当たりますので、転籍出向を会社は自由にできるかという問題になります。法理を含めた対処方法を、アドバイスします。
(1)転籍出向について
転籍出向は、会社の命令で社員が別の会社に移ることです。在籍出向と違い、社員の身分は元の会社に残りません。
社員は、元の会社と雇用契約を清算して退職し新しく転籍先(出向先)の会社に採用されることになります。つまり、その転籍先の社員としての自分が新たにできるわけです。転籍後の労働条件は転籍先の会社との雇用契約で決まりますし、服務規定や就業規則も当然転籍先の規定が適用されます。なお、いったん転籍出向した社員が転籍前の会社に戻ることは、まずありません。
そこで、定年時の退職金がどうなるかその算定方法と概算額、支払い義務のある会社など、必要なことは同意する際に必ず確かめる必要があります。
(2)転籍出向は社員の同意がない限り、認められていません
このように、転籍出向は社員の身分関係や労働条件が大きく変わりますので、会社は社員の同意がない限り転籍出向命令を出せません。
社員は転籍したくなければ、その命令を拒否すればいいのです。転籍命令を拒否したからといって、懲戒処分を受けることは通常ありません。
同意が必要なケースは在籍出向より広く解釈され、たとえ就業規則に転籍出向についての規定があっても、必ず個別に社員本人の同意が必要とされています。
なお、転籍出向は退職と採用という2つの法律行為を1つの行為のように行います。ですから、元会社からの退職と転籍先への採用は一体的関係にしなければなりません。
そこで社員が同意しても転籍先との具体的な労働条件を合意しない限り新しい雇用契約は成立しません。この場合には、転籍は成立せず、社員は元の会社との雇用契約が継続します。
(3)裁判所も社員の同意がない転籍出向は認めない傾向
転籍出向については、必ず社員本人の個別的、具体的な同意を必要とするというのが裁判所の一般的な傾向です。
就業規則に出向規定があっても包括的な合意を認めず、個別に社員本人から同意を得なければならないとしています。
(4)具体的な対処方法について
以上のとおり、法的には転籍出向は、あなたの同意がなければ命令を出せません。そのため、自身が望まないのであれば、その命令を拒否すればいいのです。ただ、現在されている仕事(業務)がなくなるようなとき、会社の存続と発展のためには社員の理解と協力が必要不可欠になるため、
1. 会社経営の目的や目標、将来発展
2. 転籍出向の必要性
3. あなたを選んだ理由
4.転籍後の労働条件など
について会社とよく話し合い、合理性、公平性、平等性などをよく判断した上で円満に解決すべきでしょう。なお、不明な点がありましたら、ご一報ください。サポートします。
Q.3 罰金制度
現在勤めている会社では、罰金を社員から取る場合があります。この在職中に取られた罰金は会社を退職する際に返ってくるものでしょうか?
Answer
あなたの相談内容の罰金制度について、どんな内容なのか理解できませんが、予測される事故や過失による罰金制度については法律(労基法16条)により禁止されています。
従業員が任意で罰則金制度を作り「その集金した金を暑気払いや忘年会費」などに充当して会費の足しにするようなケースはあるようですが、会社で制度を決めることは違法行為となります。
罰則金が退職した際に支給されるか否かは、罰則金規程の内容によると思われます。従って、罰則金規程の内容を調べてください。どんなときに罰金を支払い、何に使われるのか記載されたものがあると思われます。
不法不当な内容であると思うのであれば、罰金制度の廃止を求めるべきと考えます。いかがでしょうか? その場合は仲間と相談し、経営者と話し合ってください。
Q.4 罰金制度の不服申し立ての方法は?
業務にミスがあったとの理由で、私の事業所(社員約20名)で社員1人につき罰金1万円が、今月の給与から引かれました。そして「今後、ミス1点につき1万円の罰金を課し、翌月似たようなミスを犯した場合は罰則金を倍額にする」とも言われました。他の事業所に問い合わせたところ、罰金制度の存在すら知らないとのこと(さらに給与明細は、半年分まとめて渡されたり、残業代がつかないばかりか休日出勤の代休も取れません!)。会社に不服を申し立てる場合は、どのようにしたらよいでしょうか?
Answer
ご相談内容は、「業務上ミスが生じた際」の罰則金(損害賠償)制度と、不服申し立て手続きについてです。 労働契約を結ぶときに、会社が労働者の足かせになるような条件を付けることは、認められません。
●労働者に会社が付けてはならない条件
[賠償予定の禁止(労基法第16条)]
労働者が、契約期間の途中で会社を退職したときや、労働者の不注意で会社の備品を壊してしまったときには、ペナルティとしていくら払うというように、あらかじめ労働契約に賠償額を決めておくことは認められません。ただし、労働者の重大な過失などにより会社に損害を与えた場合には、損害賠償義務がなくなるわけではありません。
上記のほかに、[前借金相殺の禁止(同法第17条)]・[強制預金(同法第18条第1項、第2項)]などがあり、こうした労働条件の基準(賃金・労働時間・休日・休暇・残業など)は法律で決められていますが、個々の会社の具体的な職場の規律は就業規則で定められています。
(1)就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を雇用している会社では、必ず就業規則を作成して、労基署長に届けなければなりません。ここでいう「労働者」とは、いわゆる正社員だけではなく、パートタイマーなども含みます。 複数の工場や営業所を持つ会社の場合、その事業所に常時10人以上の労働者がいるときには、事業所ごとに就業規則を作成しなければなりません。また、就業規則を変更したときは、労基署長への届け出が必要です。 従って、貴社のあなたが勤務する事業所には常時20人ほどの従業員がいますので、就業規則が必要であり、労基署長に届ける義務が生じます。
(2)雇用契約を結ぶとき労働条件を明確に
ある会社に就職が決まると、就職する人(就職すれば労働者)と会社(使用者)との間で、賃金や労働時間、休日・休暇などについて、こういう条件で雇う、雇われるという約束をします。この約束のことを「労働契約」といいます。会社は労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を明らかにしなければなりません。 特に、以下に示す5項目は、労働者に書面で明らかにしなければなりません。
[書面により明示すべき労働条件に関する事項]
1.労働契約の期間に関すること
2. 仕事をする場所、仕事の内容
3. 仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換など
4. 賃金の決定、計算と支払いの方法、締め切りと支払いの時期
5. 退職に関すること
また、労働者にとっても労働契約の内容が明らかにされないまま働き始めてしまうと、後で「こんなはずではなかったのに」と思うことがあるかもしれませんので、労働契約を結ぶときには、あらかじめ労働条件を確認しておくことが大切です。
会社には、労働条件や職場の規律などを定めた「就業規則」があります。会社に就職したら、就業規則をよく読み、労働条件がどうなっているかを確認しておくことも、また大切です。
今回の場合、貴社では賃金支払い明細が賃金支払日に交付されず、半年間まとめて交付するなど、ルーズな現状が目立ちます。
賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、日にちを決めて支払わなければならないという労基法に定める賃金支払いの5原則に違反する行為となります。さらに、法定労働時間(1日8時間、週40時間労働)をオーバーして残業・休日出勤しても割増賃金は支払われず、代休も与えられないという内容は、明らかに労基法違反となります。
(3)結び(あなたの相談に対する結論)
1.労基法に照らして、どう考えるべきか?
上記、前書きで示したとおり「賠償予定の禁止」――あらかじめ労働者の不注意やミスを想定し、ペナルティとしていくら払うというように定めること――は労基法第16条に違反する行為ですし、今回お尋ねの業務ミスによる罰金1万円の強制天引きは、そのミスによる“損害金が明らかにされないまま罰金として労働者に課す行為”は、労基法第16条の精神から逸脱した内容と考えるべきです。さらに、「今後、ミス1点につき1万円の罰金を課し、翌月似たようなミスを犯した場合は罰則金を倍額にする」などは、明らかに違法となります。
2. 不服申し立て手続き
ア.まず、会社が今回強行した罰則金制度についての不法・不当性について社内の同僚と相談し、多くの仲間に呼び掛け、会社と交渉して撤回を求めてください。
イ.会社と交渉して解決できない場合は、労基署の指導を仰ぐことをお勧めします。労働者が、会社が労基法に反している事実を労基署に申告したことを理由とする解雇または、不利益扱いすることは「労基法第104条1項」により、認められません。
さらに相談が必要な場合は、お気軽にご相談ください。
Q.5 本人の知らないところで試用期間を延長できるか?
試用期間3カ月ということで入社しました。3カ月経過後も何も知らせはありませんでしたが、半年経って「まだ正社員にはなってない」と突然会社から言われました。本人への通達がないまま、試用期間を勝手に会社は延長することができるのでしょうか?また、入社前に試用期間中は社会保険に入れないと説明を受けたので、現在も未加入です。これは法的に認められるものですか?
Answer
相談内容は、試用期間延長と社会保険加入についてですね! あなたは入社の際、労働契約(雇用契約)を結びましたか? それとも口頭での約束ですか? あなたのように、後々問題が起こらないように、就職しようとする人(労働者)と会社(使用者)との間で、賃金や労働時間、休日・休暇などについて、こういう条件で雇う、雇われるという約束をします。この約束のことを「労働契約」といいます。
(1)労働契約について
会社は、労働契約を結ぶときに賃金や労働時間などの労働条件を明らかにしなければなりません。また、労働者にとっても労働契約の内容が明らかにされないまま働き始めてしまうと、後で「こんなはずではなかったのに」と思うことがあるかもしれませんので、労働契約を結ぶときには、あらかじめ労働条件を確認しておくことが大切です。
会社には、労働条件や職場の規律などを定めた「就業規則」があります。会社に就職したら就業規則をよく読み、労働条件がどうなっているかを確認しておくことが大切です。
特に次の5つの項目については、労働契約の際、労働者に書面により明示すべき労働条件に関する事項です(労基法89条)。
1.労働契約の期間に関すること
2.仕事をする場所、仕事の内容
3.仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇・就業時転換など
4.賃金の決定、計算と支払いの方法、締め切りと支払いの時期
5.退職に関すること
(2)試用期間について
あなたは、就職が決まった際に「試用期間は3カ月」と約束していたようですので、特別な理由もなく、会社が勝手に試用期間を延長することはできません。たぶん、社会保険料の負担が重いため延長したのだと思われます。従って、契約どおり正社員とするよう求めてはいかがでしょうか。
(3)各種社会保険の加入について
社会保険は、「労災保険・雇用保険・健康保険(介護保険を含む)・公的年金保険(厚生年金)」制度があります。この各種社会保険制度は、労働者のための制度です。各種社会保険の説明はしませんが、社会保険への加入は労働者を一人でも雇っている法人事業所(強制適用事業所)全てに適用されます。強制適用事業所で働く労働者は、本人が加入を希望するか否かに関わらず、全て被保険者となります。(ただし、「短期間(2カ月未満)・短時間勤務契約者は別に定める規定の適用」となります。)
会社は、試用期間中は各種社会保険制度に加入しなくてもよいと勘違いしているようですが、それは大きな間違いです。労働災害保険は会社全額負担ですが、雇用保険・健康保険・公的年金保険は、基本的に会社と労働者が折半で負担する制度です(賞与も同様負担)。
上述(2)でも触れましたが、社会保険に支払う金額が重いため、言い逃れしているとしか考えられません。従って、試用期間の延長問題と併せ、各種社会保険制度に加入するよう、勇気を持って話す必要があります。もし、加入を拒むようでしたら、最寄りの労基署もしくは社会保険事務所にご相談ください。なお、違反行為を告発したことを理由に、解雇や不利益扱いすることは禁じられています。
Q.6 会社の役員が変わり、経験のない業務の担当となり、困っています……。
外資系の企業に営業事務として年俸制の社員で入社しました。今年役員が変わった際に営業から経験のない経理の業務も担当することになりました。業務が増える一方で、さらに残業代も支払われません。体力的にも連日の残業で限界です……。
Answer
外資系の会社に勤務し、役員が変わって営業の採用であったあなたが経理の経験がないのに強引に経理の仕事も担当することになり、業務が増えて困っている始末。また、毎日残業が続き、体力的に限界で、挙句の果てに残業代も支払われていない現状。こちらのご相談への、アドバイスです。
(1)労働契約の点検を
あなたは、採用に当たって仕事の内容は営業事務であったと記されていますので、現在の会社に就職が決まったとき、労働契約を結んでいると思います。
労働契約を結ぶときには、仕事の内容、毎月の賃金、労働時間、休憩時間、年次有給休暇、残業の有無など、あらかじめ決めておかなければならないことがたくさんあります。それらを全て口頭で済ませてしまうと、後に「言った、言わない」のトラブルのもとになりかねません。そこで、労基法では使用者に対して労働契約を結ぶときには労働者に労働条件を明らかにすることを義務付けており(労基法15条)、さらに厚生労働省では、労働契約の中でも、特に書面を用いて明示されなければならない事項については、労働条件通知書を活用して労働条件を明らかにするよう示しています(同法施行規則第5条)。
<書面で明示しなければならない労働条件>
1.労働契約の期間に関すること
2.仕事をする場所、仕事の内容
3.仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換など
4.賃金の決定、計算と支払いの方法、締め切りと支払いの時期
5.退職に関すること(解雇の事由を含む)
どんな事情があって役員が変わったのか存じませんが、あなたが交わした労働契約を使用者が一方的に変更することは許されません。従って、契約に従って業務に専念できるよう話し合うことが大切です。
あなたの希望がかなえられない場合は、妥協できる範囲の内容を追求することです。労働者は体が資本です。過剰労働で病気になるようなことは、避けなければなりません。
(2)年俸制契約と残業割増賃金について
年俸制とは、会社(使用者)が、労働者の能力や仕事の成果、将来への期待などを総合的に評価して、1年間の総賃金(年俸)に反映させる賃金制度です。
「年俸制を採用すれば、残業代を支払わなくてすむ」と誤解している会社も多いようですが、原則的に年俸制とは年間所定労働時間だけ働いたときの賃金を想定していますから、時間外労働や休日労働を命じたときには、別途、割増賃金を支払う必要があります。
もし、一定の金額を割増賃金分として含んだ上で年俸額を決定するのであれば、あらかじめ「年俸○○円、うち割増賃金分××円」というように、内訳を明らかにしておかなければなりません。また、実際に働いてみた結果、事前に決められた割増賃金を超えて働いた場合にも、割増賃金の不足分を追加して支払わなければなりません。もちろん、年俸額が最低賃金額を下回ってはなりません。
(3)残業代の請求について
従って、法定労働時間(休憩時間を除いた1日8時間)を越えた労働時間は、時間外労働(残業)となりますので、請求する権利があります。 外資系の会社であれ、日本国内の企業の場合は、日本の法律が適用されます。 会社が、労基法を守っていないことを「労基署」に申し出たことを理由に、解雇したり不利益扱いすることは禁じられていますので、当事者間で話し合い解決が困難な場合は、最寄りの「労基署」または「労働相談情報センター」の指導を仰ぐことをすすめます。
Q.7 異動に伴い等級と給与が下がり納得できません。
経理部から営業部に異動になりましたが、それに伴い等級も給与も下がり、納得できません。これは、不当行為にはならないのでしょうか?
Answer
相談内容は、使用者の一方的な理由で、経理部から営業事務に異動され、等級が下げられた結果、賃金も減額となったが、これは不当ではないかという相談です ね!これらの内容は、労働条件の「不利益変更」といい、使用者は合理的な理由がなく労働者に不利に変更することはできません。以下、法理に基づいてアドバ イスしますので、参考にしてください。
(1)労働契約を結ぶときに労働条件はハッキリとすること
ある会社に就職が決まると、就職しようとする人と会社(使用者)との間で、どのような条件で雇う、雇われるという約束を交わします。この約束のことを「労働契約」といいます。
労基法では、使用者に対して、労働契約を結ぶときには労働者に労働条件を明らかにすることを義務付けています(労基法第15条)。
労働契約を結ぶときには、毎月の賃金、労働時間、休憩時間、休日、年次有給休暇、残業の有無など、あらかじめ決めておかなければならないことがたくさんあります。
それらを全て口頭で済ませてしまうと、後に、「言った、言わない」のトラブルのもとになりかねません。そこで厚生労働省では、労働契約の内容の中でも、特に以下に示す5項目は書面で明らかにするよう義務付けています。
<書面で明示しなければならない労働条件>
1.労働契約の期間に関すること
2.仕事をする場所、仕事の内容
3.仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換など
4.賃金の決定、計算と支払いの方法、締め切りと支払いの時期
5.退職に関すること(解雇の事由を含む)
(2)使用者は、合理的な理由なく労働条件を労働者に不利に変えることはできない
会社は、就業規則を作成または変更するときには、労働者側の意見を聴かなければなりません。「意見を聴く」というのは、会社が労働者側の意見を求めるということであって、労働者側の意見を採用したり、労働者の意見を反映させる義務がある、ということではありません。ですから、労働者側が、就業規則の変更に反対していても、会社が労働者側に原案を十分に検討して、具体的な意見を述べるだけの時間的余裕と便宜を与えている場合には、ただちにその就業規則が無効になるとは限りません。
しかし会社は、労働者側から意見を聴けば、いくらでも労働条件を引き下げることができるというものではありません。これはいわゆる「就業規則の不利益変更」といわれる問題で、判例では「新たな就業規則の作成又は変更によって、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは許されないが、合理的なものであるかぎり可能である」と示しています。これは言い換えると、「会社は合理的な理由がなければ、労働条件を労働者に不利になるように一方的に変更することはできない」ということを示しています(秋北バス事件 最高裁大法廷判決 昭和43年12月25日)。
なお、就業規則を作成していない会社において、労働条件を不利益に変更する場合、あるいは就業規則とは別に個別に結んでいる労働契約の内容を不利益に変更する場合については、原則として労働者の同意が必要になります。
(3)具体的見解
上記で、労働契約および不利益変更問題について、法理に基づき、説明しました。前述したように、あなたは労働契約を結ぶ際、経理の仕事で契約し、賃金はいくら、労働時間その他の労働条件は各々うんぬんである、ということで了解して勤務についたと判断します。
どんな事情があって経理から営業事務に異動を命じられたかわかりませんが、いずれにしても会社の一方的な理由での異動命令で、「営業事務は全て同一等級で賃金も同一だという理屈は(同一労働同一賃金の原則)」から理解が得られたとしても、結果として、あなたは賃金が減額となり不利益変更を受けるわけですので、同意が必要となります。そして、不当な扱いには変わりないと判断します。
従って、なぜ経理から営業事務に異動を命じたのか理由を明らかにさせ、その上で、あなたに何ら落ち度がなければ、経理業務を継続させるよう求めるべきではないでしょうか。
そして、それがかなわない場合であっても、賃金は維持するよう求めるべきと考えます。
Q.8 労働条件の変更はどのように交渉したらよいでしょうか?
昇給の時季に今の労働条件を変えてほしいと考えています。昨年は口頭での約束でしたので、今年はきちんと書面にしてもらいたいのです。どのように交渉したらよいでしょうか?
Answer
ご相談内容は、労働契約内容の変更についてですね!簡単にアドバイスしますので、ご参考ください。
(1)労働契約とは
ある会社に就職が決まると、就職しようとする人と会社(使用者)との間でどのような条件で雇う、雇われるという約束を交わします。この約束のことを「労働契約」といいます。
労基法では、使用者に対して労働契約を結ぶときには、労働者に労働条件を明らかにすることを義務付けています(労基法第15条)。労働契約を結ぶときには、毎月の賃金、労働時間、休憩時間、休日、年次有給休暇、残業の有無など、あらかじめ決めておかなければならないことがたくさんあります。それらを全て口頭で済ませてしまうと、後に「言った、言わない」のトラブルのもとになりかねません。
そこで厚生労働省では、労働契約の中でも特に重要な事項について、下記の5項目は書面で明示することを義務付けています(同法施行規則第5条)。
<書面で明示しなければならない労働条件>
1.労働契約の期間に関すること
2.仕事をする場所、仕事の内容 仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換など
3.賃金の決定、計算と支払いの方法、締め切りと支払いの時期
4.退職に関すること(解雇の事由を含む)
以上の5項目が書面による明示義務とされています。
(2)労働契約変更手続きについて
会社には、就業規則があります。就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律、そのほか労働者に適用される各種の定めを明文化したもので、いわば職場における法律のようなものです。小規模の会社では、就業規則を作成していない会社もありますが、明文化した規定がなく、労働条件がそのつど決められるようでは、トラブルが生じる原因になりかねません。
大勢の人の集まりである会社の秩序を守り、統一的に事業を運営していくためには、労働条件や服務規律などを明らかにした就業規則を作成する必要があります。従って、あなたの要望する労働条件を就業規則の手続きに従い、申請することをお勧めします。
(3)就業規則の作成義務(労働基準法第89条)
常時10人以上の労働者(いわゆる正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員なども含まれます)を雇用している会社は、必ず就業規則を作成して、労基署長に届けなければなりません。
工場や営業所など、労働者の就業場所(「事業場」といいます)が複数に分かれているときには、常時10人以上の労働者が働いている事業所ごとに、就業規則を作成しなければなりません。また、就業規則を変更したときも労基署長への届け出が必要です。
(4)あなたの相談に対する具体的アドバイス
あなたの勤める会社は小規模事業所のようですが、就業規則がある場合は、その規則に従って、労働条件変更手続きを行ってください。なお、就業規則などがない場合は、上司または使用者(社長)とよく相談し、新たに結んだ労働契約書を書面で確認することがベストと考えます。