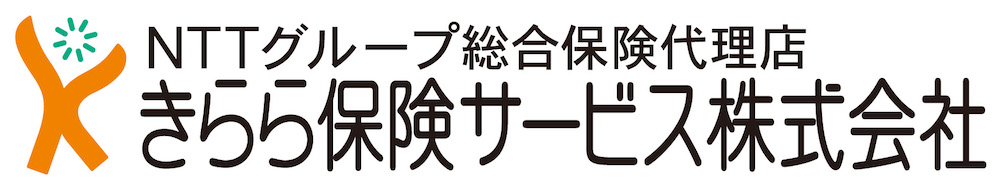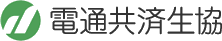Q.1 「次の人が来るまで、いてもらう」と言われてしまいました
現在勤務している会社に、退職届を契約書どおり2週間前に提出しましたが、「次の人が来るまで、いてもらう」と言われました。次の会社も決まっているため、必要書類を提出して、出社しないようにしたいのですが……。
Answer
(1)退職に関するルール
労働者からの一方的な解約を辞職(任意退職)といい、労働者と使用者との合意によって労働契約を終了させるのを合意退職といいます。期間の定めのない労働契約の場合は、どのような理由があっても、自由に会社を辞めることができます。しかし、社員がある日突然、退職してしまったら、使用者も、残された同僚も、困ってしまいます。従って、退職に関する事項は、就業規則などに「退職の申し出は退職予定日の1カ月前までに申し出ること」というように、あらかじめ後任の手配や、事務引き継ぎ期間を見込んで退職日までの申し出期間を定めているのが一般的です。
退職の申し出をするときは、就業規則などに退職のルールがどのように定められているのかを確認し、そのルールに基づいて事前に上司とよく話し合うのが、円満退職の条件とされています。
(2)対処策
あなたの場合、退職届を「労働契約書どおり」提出しているので問題ないと思います。しかし、会社は業務が滞ることから、“次の人”が決まるまでいてほしいと言っているようです。その事情も理解できるでしょうから、あなたは早く“次の人”を採用するよう会社に促してください。その上で、退職期日までに次の人が採用されないようであれば、上司との間で業務の引き継ぎを行い、けじめをつけて退職することがベターと考えます。 会社に必要書類だけを送付して辞めるのは後味が悪いと思いますので、適切な順序を踏んで、後に問題が生じないよう、配慮してください。
Q.2 雇用期間の途中では辞められないの?
会社に退職の意思表示をしたところ、「雇用期間の途中なので、辞めさせることはできない」と拒否されました。雇入通知書には「退職するときには、2週間前に意思表示をすればよい」と書いてあります。期間の終了まで、辞めることはできないのでしょうか?
Answer
一般的に退職は円満に行うことが大切ですので、労働者が自らの意思によって退職の申し出をするときには、後任の手配や仕事の引き継ぎなど会社側の都合を考慮した上で、ルールに従い、事前に人事権のある上司に申し出ることが円満退職のポイントであることを念頭に置く必要があります。
さて、あなたの場合のルールですが、契約期間の定めがある労働契約を期間満了前に終了させるという問題になります。
1.期間の定めがある労働契約の場合、会社と労働者(あなた)が契約期間を定めた上で労働契約を結んだのですから、お互いにその契約期間を誠実に守る義務があります。契約期間の満了前に退職することは、契約違反になりますので、労働者(あなた)が契約期間満了前に勝手に退職することはできません。
2.就業規則や雇入通知書に契約期間途中であっても退職できる定めがある場合には、それに従って退職することになりますが、特段の定めがない場合にも、なるべく合意解約ができるよう、十分話し合うことが大切です。
3.残念ながら会社の理解が得られなかった場合であっても、やむを得ない事情(※)があるときは、労働契約の解除を申し出ることができますが、それが労働者側の一方的な過失による場合には、会社から損害賠償請求を起こされる可能性があります(民法628条)。 ※「やむを得ない事情」とは、仕事の継続により労働者の身体、生命に対する危険が予測される場合、近親者の介護の必要、家庭の事情の急激な変動などが考えられます。
4.あらかじめ明示されていた労働条件と実態が異なっていたことを理由に(長く働かされたり、安い賃金で働かされたなど)、労働者が退職を申し出る場合には、雇用契約をただちに解除することが認められています(労働基準法〈以後、労基法〉15条2項)。
以上がルールです。
そこで、ご相談ですが、まず雇入通知書に明示されている「自らが退職を希望し、辞める2週間前に意思表示すること」の箇所について、契約期間途中の退職に関する定めなのか、会社の人事担当に確認する必要があります。途中退職の定めだとすれば、それに従って退職するということになります。
次に定めがない場合ですが「合意解約」、すなわち、あなたと会社との合意による解約を追求するしかありません。冒頭で述べたように、相手の立場も真摯(しんし)に受け止めながら、あなたのやむを得ない事情について円満に話し合って、解決してください。
Q.3 ボーナスが支給される月に退職すると支給されなくなるのではと不安です。
転職を考えています。冬のボーナスを期待して12月末日で退職すると伝えたとき、ボーナスが支給されなくなる可能性があるのでは……と不安です。支給月に退職する場合も、ボーナスは支給されるのでしょうか?
Answer
●賞与の支給条件について
賞与は、毎月支払われる労働に対する賃金と異なり、法的にもその支払いが義務付けられているものではありません。ただし、就業規則などで賞与を支払う旨を改定している場合には、使用者に賞与の支払い義務が生じますが、トラブルとなるのは、賞与支給日に会社に在籍していることを支給要件とするケースで、あなたの心配も、例外ではありません。その法理と対処策について、アドバイスします。
(1)支給日在籍要件
支給日在籍要件とは、賞与の算定期間(たとえば、夏は12月~5月、冬は6月~11月)の全部または一部に就労していても、賞与の支給日前に退職した従業員に賞与を支給しないとする条件です。判例では、賞与の性格から、あるいは月例賃金とは性質を異にするといった理由から、支給日在籍が要件として就業規則などで明確に定められている場合には、それが支給要件であり、その支給要件を満たしていない人には支給しなくても、労基法24条に違反しないとしています(名古屋地裁 判決)。また、当事者間で従来からそのような取り扱いが確立しており、労使慣行が成立していると認められる場合は支給日に在籍していない人に賞与を支給しなくても、差し支えないとしています(最高裁判所 判決)。
(2)賞与支給の可否の判断
通常、賞与はそれが使用者の恩恵的給付と見られる場合を除き、支給対象期間の勤務に対応する賃金と考えられ、そこには生活補充的意味および将来への労働への意欲向上策としての意味が込められているといえます。従って、賞与が賃金としての性格を持ち、その支給要件を満たす従業員は、それに対する請求権を有するとされています。
そこで、賞与支給の可否ですが、就業規則に、1)賞与を支給する旨の規定、2)賞与支給額・計算方法、3)支給日在籍要件がどう定められているかを確認し、かつ不明なところは会社に説明を求め、その可否を判断してください。
Q.4 退職するときに残りの年休消化はできない?
来月末付けで、退職を予定しています。給与は15日締めになっているので、16日~30日までは日割りの賃金をもらうことになっています。その間に、残りの有給休暇を取る予定でいたのですが、以前退職した人は、日割り賃金の対象期間に有給休暇を取っても、その日給は支給されなかったというのです。残りの有給休暇はもう取れないのでしょうか?
Answer
ご相談内容は、退職手続きの問題になります。まず、基本的なことから申し上げますと、退職の申し出は原則的に、労働者からの口頭の意思表示で足り、会社の承認は必要ありません。しかし退職手続きには、あなたのご質問のほか、退職金や雇用保険の請求、後任の手配や仕事の引き継ぎなどがありますので、会社側の都合も考慮し、円満に退職するのがよいでしょう。
言うまでもなく、職場の規律は就業規則に定められていますので、念のため就業規則をよく読み、退職に関する事項がどうなっているか確かめることが大切でしょう。このことを前提にし、法的根拠を含め、ご質問にお答えします。
(1)退職時の賃金の清算
退職時の賃金の清算は、使用者は労働者の退職の場合に、労働者から請求があった場合には、所定の支払日に関わらず、 請求から7日以内に賃金を支払うほか、積立金、保証金、貯蓄、その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなけ ればならないと定められています(労基法23条)。
(2)退職に伴う年休の消化の請求
1.年休請求権
年休を請求する権利は、労基法により認められた権利であるため、労働者が請求したときには、使用者はその時季に年休を与えなければなりません。すなわち、労働者はいつでも自由に年休を取ることができ、年休をどのように利用するかも自由で、使用者の承認は必要ありません(労基法39条4項)。
2. 時季変更権
使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、労働者の指定する時季を変更することができます(労基法39条4項)。
(3)ご相談(退職時の未取得年休の一括取得)のケース(法的判断と対処策)
退職しようとする労働者が、年次有休休暇の残日数を取得することを見込んで退職日を定めて退職願を提出したときは、退職する日までは労働関係が継続しているため、その年次有給休暇(以後、年休)の時季の指定に対しては、先述の事業の正常な運営を妨げる理由のない限り、変更権を行使することは許されません。このような事情がなければ、指定した時季どおりに労働者は年休として休むことができます。
特に退職時に労働者から未取得年休全日について、一括して取得請求がなされた場合、使用者は拒むことができないのは、使用者の時季変更権は他の時季に年休を与えることが前提となり、退職時には他の時季に年休を与えうる可能性がないからです。なお、事業の正常な運営を妨げる場合は、単なる業務繁忙程度で変更することは認められていないというのが、裁判例です。
従って、あなたは退職に伴う年休の取得を請求する権利があり、会社が主張できるのは時季変更権だけになります。退職時には行使ができないので、拒むことはできません。また、年休取得日は日割賃金の支給対象にしないとする使用者の主張は、労基法39条6項に違反するため、許されるものではありません。さらに、使用者は年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません(労基法136条)。
会社と話し合いで解決しない場合、最寄りの労働基準監督署(以後、労基署)にご相談ください。専門の職員が相談に乗ってくれるはずです。
繰り返しになりますが、なるべく円満に話し合って解決してください。
Q.5 1年の途中で辞める場合は有給休暇を全て消化できない?
10月に退職するのですが、「10月の後半に有給休暇を取りたい」と会社に申し出たところ、「有給休暇は、1年間の勤務に対して取得日数が決められている。今年度は1年間勤務しないので取得できない」とのことでした。1年の途中で退職する場合は、全ての有給休暇を消化できないのでしょうか?
Answer
ご相談は年次有給休暇制度(以下年休)の問題になります。まず大切なことは、職場の規律は労基法の基準に沿って、就業規則で定められているということです。退職に当たっては、就業規則をよく読み、退職手続きや年休がどうなっているかを確認してください。
このことを前提に、年休が法律でどう定められているかについて、アドバイスします。
(1)年休請求権
年休を請求する権利は、労基法により認められた権利ですから、労働者が請求したとき、使用者はその“時季”に年休を与えなければなりません(労基法39条4項)。
年休制度が設けられた趣旨は労働者に日頃の精神的、肉体的な疲労回復の機会を与え、人間らしい健康で文化的な生活を保障させるためです。 年休を取る権利は、労働者が6カ月以上会社で働いて、かつ労働日の8割以上出勤したときという要件が満たされることで法律 上当然に生じるもので、労働者の請求を待って生じるものではありません。従って、労働者が年休を取りたい場合は、その日時を指定して、 使用者にその旨を通告すればそれで足り、それ以上の手続きは原則不要というのが、最高裁判所の判例です。
(2)時季変更権について
しかし、会社の忙しい時に、たとえば労働者に一斉に年休を取られたのでは、会社はやっていけません。そこで労基法では、両者の調整を図って、労働者が請求した時季に年休を与えると事業の運営に支障をきたすという場合には、使用者は他の時季に振り替えて年休を与えてもよいことにしました。これを時季変更権と呼んでいます(労基法39条4項)。注意しなければならないのは、適用となる事例は、あくまで会社が正常に運営できないという具体的な事情があるときで、「ただ忙しいから」という理由だけで、労働者が休みたい日に休ませないということはできません。
(3)年休の買い上げ
年休を与えず、それと引き替えて金銭で支払うこと(年休の買い上げ)は違法とされていますが、退職の際に消化できなかった年休を買い上げることは、許されています。会社にそのような制度があるかどうか、確認してください。
(4)退職時の未取得年休の一括取得
退職時に労働者から未取得年休全日について、一括して取得請求(労働者の時季指定)がなされた場合、 使用者は拒むことはできません。使用者の時季変更権は他の時季に年休を与えることが前提となり、退職時にはその可能性がないからです。 また、使用者は年休を取得した労働者に対して、賃金の減額、その他不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません(労基法136条)。
(4)退職時の未取得年休の一括取得
年休の請求に関して、会社に認められているのは時季変更権だけであり、退職時にはその可能性がないので、未取得年休全日についての一括取得請求を拒むことはできません。従って、「1年間の勤務に対して取得日数が定められている」とする会社の主張は誤りです。
労働契約は退職によって終了しますが、退職に当たっては、退職金や離職票の発行などの手続きもありますので、会社と冷静に話し合って円満に解決してください。会社と話し合いがつかない場合は、労基署にご相談ください。専門の職員が相談に乗ってくれ、場合によっては会社に指導や勧告をしてくれます。
Q.6 退職時の年休の買い取りは、どこの職場でも対応してもらえますか?
希望どおりの年休がもらえなかったため、年休(40日)の消化ができず、退職日を決められた場合はどうしたらよいのでしょうか? また、退職時の年休買い取りも可能と聞きましたが、どの職場でも対応してもらえるのでしょうか?
Answer
ご相談内容のポイントは、退職の際、年休を全て(40日)消化することが法理に照らし可能かどうか、ということです。
(1)労働契約、就業規則(職員規定)の点検を
あなたの勤務する病院に労働組合が存在しますか? 労働協約で退職の際、年休に関する規定が定められている場合は、その定めに従ってください。労働協約にない場合は、就業規則にはどのように定められているかを調べ、その内容に従ってください。
(2)年休の取得と時季変更件
労働者は、いつでも自由に年休を取得することができ、利用理由は問われることはありません。また、使用者は労働者が請求した日に年休を与えなければなりません(労基法39条5項)。
しかし、【Q-5】の(2)にあるとおり、一度に多数の者が休暇を取ると会社(事業所)の正常な運営ができなくなることがあるため、会社は事業に支障が生じるときに限り、年休を他の日に振り返ることができます(労基法第39条第4項 時季変更権)。
ここでいう、「事業に支障が生じる」というのは、誰が見てもそのときに労働者に会社を休まれたら会社が正常に運営できない、という具体的な事情があるときです。ですから、単に忙しいからという理由だけで労働者が休みたい日に休ませない、ということはできません。
なお、会社は年休を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません(労基法第136条)。
(3)年休の買い上げが可能かどうか
法的には原則的に買い取りは違法とされていますが、退職の場合に限り、労使 (当事者間)の合意があれば、買い取りもできますし、年休の余剰日数に合わせ退職することも可能です。従って、特に定めがない場合は、話し合いによって解決する以外に方法はありません。
(4)退職時の一括取得
退職時に未取得年休全日について一括して時季指定(年休取得の請求)がされた場合、使用者は時季変更権を行使できず、拒むことができません。使用者の時季変更権は、他の時季に年休を与え得ることが前提となり、退職時にはその可能性がないからです。
(5)結論(対処策)
退職時の未取得年休全日について、年休取得の請求をされた場合、使用者は拒むことはできませんし、年休の買い取りは退職の場合に限り、“当事者間の合意があれば法的には可能です”ので、誠意を尽くし、話し合い、合意できるよう努力してください。
Q.7 残りの年休を全て消化し、賞与も退職金も受け取って退職したい
賞与月に退職を予定しています。退職金もあるので、賞与を減額されたり、支給されないということはありませんか? 希望としては、今年度の年休を消化して賞与も退職金も受け取って退職したいのです。
Answer
ご相談は専門的になりますが、ボーナスについては「ボーナスの法的性格と請求権の存否および支給日在籍条項」、そして年休については「退職に伴う未取得年休消化の請求」という問題になりますので、法的判断を含めてアドバイスします。
(1)賞与(ボーナス)
1.賞与の法的性格と請求権の存否
賞与は夏と冬にボーナスとして支給されるのが通例で、就業規則の中に賞与などの規定を設けるのが一般的です。その内容はたとえば、「賞与は毎年6月および12月に会社のその期の営業成績を考慮して支給する」というように、支給期間、支給基準などについて簡単な規定を置くことが多く、また会社に労働組合があるときは、団体交渉で支給額や計算方法など、細部がその都度決められています。基本的に賞与は、支給対象期間の勤務に対応する賃金と考えられますが、それには功労報償的な意味でなく、生活補填的意味および将来の労働への意欲向上策の意味が込められているとされています。従って、賞与が賃金としての性格を持ち、その支給要件を満たす従業員には、それに対する請求権を持っているとされています。
2. 支給日在籍条項(要件)
賞与請求権をめぐりトラブルとなる最大の問題は、労働者が賞与算定対象期間の全部、または一部において就労していたにも関わらず、賞与支給日に在籍していないことを理由に、賞与を支給しないことが許されるかという点にあります。これが「支給日在籍条項」になり、このような支給日在籍条項の効力をどのように解すかが、問題になります。 現在、賞与の賃金性などから無効とする説と有効となる説が対立していますが、裁判例は次のとおりです。
1)賞与の性格から、あるいは月例賃金とは性質を異にするといった理由から、「支給日在籍(職)」が要件として就業規則や労働協約などで明確に定められている場合、それが賞与の支給要件であり、その支給要件を満たさない人には支給しなくとも労基法24条に違反しないとしています(名古屋地裁 判決)。また、当事者間で従来からそのような取り扱いが確立しており、慣行が成立していると認められる場合、支給日に在籍していない人に賞与を支給しなくても差し支えないことになります(最高裁判所 第一小法廷判決)。
2) 賞与は、一般的に一定の賞与計算(支給対象)期間内に、その人の勤務に対して、一定期日に支給されるもので、その計算期間を満足に勤務した人は例え賞与支給期日までに退職しても、特段の定めがない限り賞与請求権を有し(東京高等裁判所 判決)、また、賞与計算期間の一部のみ勤務して途中で退職した人は、特段の定めがない限り、計算期間中の勤務時間の割合に応じて同様の請求権があるとされています(東京地方裁判所 判決)。
(2)退職に伴う未取得年休の請求
1.年休請求権
年休を請求する権利は、労基法に認められた権利ですから、労働者が請求したとき、使用者はその時季に年休を与えなければなりません(労基法39条4項)。年休をどのように利用するかは、労働者の自由で使用者は休暇の理由次第で、年休を与えなかったりすることはできません。
2.時季変更権
使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、労働者の指定する時季を変更できます(労基法39条4項)。
3.退職時の一括取得
退職時に未取得年休全日について、一括して年休取得の請求がされた場合、使用者は時季変更権を行使できず、拒むことができません。使用者の時季変更権は、他の時季に年休を与え得ることが前提になり、退職時にはその可能性がないからです。
4.年休取得と不利益扱い
使用者は、年休を取得した労働者に対して賃金の減額、その他不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません(労基法136条)。
以上が賞与と年休に関する法理になります。
(3)法的判断と対処策
そこで年休を全て消化し、賞与も退職金も受け取って退職したいという件についてです。
1つ目は賞与ですが、「支給日在籍」が要件となるでしょう。前述したように、就業規則や労働協約あるいは労使慣行などで支給日に在籍していることが賞与の支給要件として定められていれば、それが決定的意味を持つことになりますので、それらを確認する必要があります。減額の心配をしていますが、特段の定めがない限り、支給日に在籍していれば賞与請求権はあると考えます。
2つ目は年休取得ですが、退職時の未取得年休全日についての一括取得になります。年休の請求に関し、会社に認められているのは時季変更権だけになり、退職時には使用者は時季変更権を行使できないため、一括取得請求を拒むことはできません。
3つ目は退職金ですが、就業規則などの定めによります。退職金は、支給するか否か、支給基準がもっぱら使用者の裁量に委ねられた恩恵的給付の場合は賃金ではありませんが、就業規則(労働契約)などでそれを支給すること、その支給基準が定められており、使用者に支払い義務のあるものは賃金と認められます。
Q.8 賞与の減額に納得がいきません!
賞与支給月の末日に退職しました。賞与は支給されたのですが、大幅に減額され、査定期間や査定方法、減額された理由などが不明です。労働組合がなく、就業規則も配布されていません。減額分を会社に請求したいと考えています!アドバイスをお願いします。
Answer
ご相談は賞与の減額の有効性の問題になりますので、法理を含めてアドバイスします。
(1)賞与の支給要件
賞与は、基本的には支給対象期間の勤務に対応する賃金と考えられていますが、そこには功労報償的な意味だけでなく、生活補填的意味および将来の労働への意欲向上策としての意味が込められています。就業規則などで賞与を支給する旨の抽象的規定があっても、支給率や額について、使用者の決定がなければ具体的な請求は発生しないとされています。また、賞与のうち、成績査定分に関して査定が労基法3条(均等待遇)などに違反し、あるいは裁量権を逸脱したような場合を除けば原則として、使用者の裁量に委ねられているとされています。
なお、旧労働省通達(昭和22年9月13日)では、賞与は定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものと定義し、労基法11条の賃金であり、労基法の規定が適用されるとしています。
(2)減額、不支給の有効性
就業規則で賞与の支給条件が明白になっている場合は、賞与も賃金です。そして、労働の提供に対する対価には月例賃金と賞与との双方が含まれます。賞与算定期間中に労働したにも関わらず、一定の事由により、その対償としての賃金の全部また一部を支給しない旨を定めることは、労基法91条にいう減給に当たるので、この制限を超えた賞与の減額の定めは、労基法91条に違反することになります(札幌地方裁判所 判決 昭和50年3月14日)。
(3)対処策
そこでご相談についてですが、1)賞与が賃金に当たるか、2)減額部分は減給の制裁に当たるのかが判断のポイントになるため、就業規則にどう定められているかを確認する必要があります。就業規則に定めがあれば賃金となりますので、次は減給の理由とその額が労基法91条に違反しないかの確認になります。
そこで確認の方法ですが、会社の給与担当に直接聞くか、文書で請求するしかなく、内容証明郵便などで行えば、証拠にもなります。減額部分の請求権の存否は、以上の判断結果になるでしょう。賃金の請求権は2年間(労基法115条)ですので、退職後も請求できます。
Q.9 退職月の給与計算方法は?
20日締め、当月25日払いの給与体系の会社を退職し、退職月の締め後の給与(21日~末日分)も翌月ではなく、退職月に支給してもらいました。しかし、その部分だけ「調整手当」という名目だけで、詳細がありません。日割給与の際は「[基本給+調整手当+交通費(通勤手当)]÷出勤日数]と聞いたことがあります。これで計算すると、調整手当分がだいぶ少ないのですが……。
Answer
ご相談内容は、中途退職の際の端数日賃金計算になります。
問題の賃金支払いについてですが、基本的な内容は、それぞれの企業に就業規則が存在し、それに従って運営されています。基本給表や諸手当の変更がしばしば行われますので、利用上の便宜を図るため、別規定として「賃金規定」により賃金体系、給与の計算と支給などを定めています。
従って、まず社内の規定ではどうなっているかを確認してください。「他社では、自分の主張どおり支払われていると聞いたことがあるので、会社の支払方法は違っているのではないか」との主張ですが、会社によってそれぞれ規則(規定)が異なりますので、一概に貴社の規定が誤りであるとは言い切れません。貴社の諸規則を調査し、適正に運用されているかを確認することが大切だと思います。
(1)就業規則の賃金規定の確認
中途退職の場合、賃金計算方式が記載された規定があると思いますので、
1. 基本給
2. 諸手当
3. 通勤手当
などが、その規定に従って計算されているかどうかを確認してください。
(2)疑問点の担当者との話し合い
会社の規則に照らし、正当に支払われていない場合は、納得できるまで話し合ってみてはいかがでしょうか。会社によっては、諸手当(調整手当)などは月の出勤日数が2分の1未満の場合、全額カットされる会社も存在します。
交通費は通常、定期代が支給され、退職の際に清算するのではないでしょうか。
(3)他社との比較
基本的に、貴社と他社では就業規則、賃金規定・賃金体系などは異なります。従って、「他社では『[基本給+調整手当+交通費(通勤手当)]÷出勤日数=支給』と聞いたことがある」というのは、あくまで他の会社の規定です。貴社の規定とは異なるため、適用されません。
(4)貴社に賃金支払い規定が存在しない場合
貴社に、上記規定が存在しない場合は、「基本給・調整手当・交通費など」を合計した金額を日割り計算で支払うよう交渉すべきと考えます。いかがでしょうか?
(5)話し合いで解決がつかない場合
法律的には、労基法に抵触しなければ、貴社の規定に従うことになります。もし納得できる解決が得られない場合は、最寄りの労基署にご相談ください。
Q.10 退職後の不払い残業代の請求方法は?
不払いの残業代を会社に請求したいと考えていますが、残業時間が正確にわかっている分と不明確な分とがあります。退職後の請求なのですが、どのような方法がありますか?
Answer
ご相談は、残業代未払いに対する対処の仕方の問題になりますので、法的根拠を含めてアドバイスします。
(1)残業代(割増賃金)請求権
1.実労働時間が法定労働時間(1日8時間と1週40時間)を超えた場合、法定休日(週1回)および午後10時から午前5時までの間に労働した場合(深夜労働)は、その時間またはその日の労働について、通常の労働時間または労働日の賃金の25%以上の率(時間外労働および深夜労働)または35%以上の率(休日労働の場合)で計算した割増賃金が請求できます(労基法37条)。この割増賃金は、就業規則や賃金規定に定めがなくても、当然に請求ができます。
2. 労基法36条(労使協定の締結・届け出)を遵守せず違法に法外残業(時間外労働)または休日労働をさせた場合にも、割増賃金の支払い義務は発生します(最高裁判所判決 昭和36年7月14日)。
(2)残業代の未払い
1.残業代未払いは労基法違反であり(労基法37条)、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)をもって、禁止されています(労基法119条1号)。
2. 割増賃金を裁判で請求する場合は、同額の付加金を併せて支払うよう請求できます(労基法114条)。
(3)使用者の実労働時間の把握義務
1.使用者には、実労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間を正確に把握し、賃金を支払う義務があります。従って、働いた時間がわからないなどと使用者が弁解することは本来許されないことです(労基法108条/労基法施行規則54条)。
2. 厚生労働省は2001年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準」として
ア.労働日ごとの始業、終業時刻を把握すべきこと
イ.始業、終業時刻の確認方法
i.使用者自ら確認し、記録すること
ii. タイムカード、ICカードなどの客観的な記録で確認すること
ウ.労働時間の記録は3年間保存すること を通達しました。この通達は、いわゆるサービス残業をなくすことを目的としたものです。
以上が、ご相談に関する法的根拠になります。
(4)対処策
次に残業代金未払いに対する対処の仕方について、2点アドバイスします。
1つ目は証拠の確保と請求です。
残業代算定の裏付けとなる労働時間管理記録(タイムカード)、業務記録(日報)、就業規則などを確保し、その上で請求することになります。実質的な証拠収集が困難な場合は、あなた自身が作成した労働時間メモも証拠となりますが、その場合は、メモの具体性(労働時間と内容)と信用性が重要となりますので、実際の業務内容を詳細に記載しておくことや、誰か別の仲間に確認してもらうなどの工夫が必要です。
2つ目は、労働基準監督署(以下、労基署)の活用です。
残業代未払いは労基法違反ですので、労基法違反を取り締まる行政機関である労基署に労基法違反を「申告」(労基法104条)するのが最も有効な対処方法です。労基署には臨検、尋問、書類提出要求などの権限が与えられていますので(労基法101条)違反を申告することにより、労基署が使用者に対して調査し、支払いを勧告し、それにより支払われる場合があります。
まずは、申告する前に労基署にご相談ください。なお、労基署の利用で解決しない場合、裁判所の利用の方法がありますが、訴訟においては実労働時間の立証や費用の問題が発生しますので、現実的な対応とはいえません。従って、粘り強く労基署に掛け合って、解決すべきでしょう。また、賃金(残業代)に関する消滅時効は2年ですのでご注意ください。
Q.11 一方的に退職の申し出をした日に辞めたら、訴えられる?
アルバイト先の事業主に、私の方から一方的に「今日で退職したい」と申し出ました。 後日、賃金について問い合わせたところ「これまでの賃金は支払う」と言われましたが、「訴える」とも言われました。訴えられるようなことはありますか? また、その場合、どのようなことが考えられますか?
Answer
ご相談内容は、突然、退職の申し出をし、当日付けで退職した(アルバイトを辞めた)ことについて、問題があるか否かについてですね。法理に基づきアドバイスしますので、ご参考にしてください。
(1)労働契約を結ぶとき、労働条件ははっきりと
ある会社に就職が決まると、就職する人(就職すれば労働者)と会社(使用者)との間で、 どのような条件で雇う・雇われるという約束を交わします。この約束のことを「労働契約」といいます。
労働基準法(以下労基法)では、使用者と労働契約を結ぶときには、労働者に労働条件を明らかにすることを義務付けています(労基法第15条)。 労働契約を結ぶときには、毎月の賃金、労働時間、休憩時間、休日、年休、残業の有無など、あらかじめ決めておかなければならないことが、たくさんあります。それらを全て口頭で済ませてしまうと、後に「言った・言わない」のトラブルのもとになりかねません。そこで厚生労働省では、労働契約の内容の中でも、特に書面を用いて示さなければならない事項については、「労働条件通知書」などで労働条件を明らかにするように示しています(労基法施行規則第5条)。これは、雇用形態「正社員、パート、アルバイトなど」に関係なく、全ての労働者に義務付けられています。
<書面で明示しなければならない、労働条件>
1.労働契約の期間に関すること
2. 仕事をする場所、仕事の内容
3. 仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換など
4. 賃金の決定、計算と支払いの方法、締め切りと支払いの時期
5. 退職に関すること(解雇の事由を含む)
(2)退職のルール
一般的に、労働者からの申し出によって労働契約を終了することを退職(自己都合退職)といいます。あなたの退職の申し出は、自己都合退職のようですので、この場合について説明します。
労働者がある日突然退職してしまったら、使用者も、また残された同僚も困ってしまいます。そのため、一般的には就業規則(雇用契約書)などに「退職の申し出は、退職予定日の14日前までに申し出ること」というように、あらかじめ、後任の手配や事務引き継ぎ期間を見込んで、退職日までの申し出期間を定めておくことが多いようです。
退職の申し出をするときには、まず就業規則(雇用契約書)に退職に関するルールがどのように定められているかを確認し、そのルールに従って、事前に上司とよく話し合うことが大切です。なお、退職の申し出に当たっては、雇用期間の定めがある労働契約を結んでいる場合とそうでない場合では、次のようにルールが異なりますので、注意が必要です。
1.契約期間の定めがないとき
契約期間の定めがない労働契約を結んでいる場合には、就業規則(労働契約書)がある場合は、その規定に従って、退職届を提出するようにしましょう。就業規則に定めがない場合は、 労働者は少なくとも2週間(14日)前までに退職の申し出をすることによって、いつでも労働契約を解除することができます(民法627条第1項)。この申し出は、原則的には労働者からの口頭での意思表示で足りるとされていますが、行き違いのないよう、文書で「退職届」などの手続きを踏む方が無難といえます。
2. 契約期間の定めがあるとき
契約期間の定めがある労働契約(有期労働契約)の場合、会社と労働者が、 契約期間を定めた上で労働契約を結んだのですから、お互いに契約の内容を誠実に守る義務があります。 契約期間満了前に退職することは契約違反ですから、契約期間満了前に、勝手に退職することはできません。就業規則(労働契約書)に、契約期間途中であっても退職できる定めがある場合には、それに従って退職することになりますが、特段の定めがない場合には、なるべく合意解約できるように、十分話し合うことが重要です。 また、残念ながら会社の理解が得られなかった場合であっても、やむを得ない事情があるときに限り、 労働契約の解除を申し入れすることはできますが、それが労働者側の一方的な過失による場合には、会社から損害賠償請求をされることもあります(民法第628条)。 「やむを得ない事情」とは、仕事の継続により労働者の身体、生命に対する危険が予測される場合、近親者の介護の必要、家庭の事情の急激な変動などが考えられます。もし、損害賠償請求された場合には、その請求内容が適切なものか、損害賠償に応じるべき範囲など、お互いに納得できるまで十分に話し合うことが必要です。
3. あらかじめ明示された労働条件と相違していた場合 労働者は、あらかじめ明示された労働条件と実態が異なっていたことを理由に、ただちに労働契約を解除することができます(労基法第15条第2項)。 これは、有期労働契約の契約期間中であっても同様です。
(3)事業主の損害賠償請求で「訴えてやる」の言葉
あなたは、退職日当日、事業主に対し一方的に退職の申し出をし、退職されたようですが、何かトラブルでもあったのでしょうか?それとも、身勝手な行動をしてしまったのでしょうか?
もし、契約期間が満了日を過ぎていて退職すると申し出たのであれば、何ら問題は生じないと思います。しかし、あなたの言葉を額面どおり受け止めると、賃金を請求した際、事業主から賃金は支払われるものの、その後 「訴えてやる」と公言され、困惑しての今回のご相談であると捉えられます。もし、身勝手に退職日当日、一方的に辞めますと申し出たのであれば、社会人としては常識外れの行動です。
上記2項で述べたように、退職するには一定の社会的ルールがあります。今後、退職の申し出をする場合には、社会的ルールを守るようにしてください。
(4)今後の対応
さて、問題はあなたが勝手に退職したことを理由に、事業主が「損害賠償を請求する」と言っていることについてですが、あなたの退職申し出の態度に対し、事業主は感情的に「訴えてやる」と言葉を発したようにも受け取れます。まだ、事業主は何ら「訴え」の行動を起こしていないようですので、しばらく静観してみましょう。
具体的な訴えの内容が明らかにされない段階で心配しても、何も始まりません。相手の出方を見た上で、今後の対応策を考えましょう。
また、あなたは未払い賃金と損害賠償請求が“相殺”されることを心配されているようですが、その心配はありません。勝手に損害賠償金や会社から前借した賃金などを一方的に相殺することを、労基法第17条で禁止しているからです。
Q.12 休職後に退職する際、残りの年休をすべて消化することは可能?
現在休職中ですが、休職(60日間)後に残りの有給休暇(30日間)を全て消化して退職することは可能ですか?
Answer
ご相談内容は、「一定期間休職し、その後に年休を消化し退職することが可能かどうかについてアドバイスを……」ということですね。 結論から先に申し述べますと、退職届の提出は、労使間のルールによりますので、定めがない場合は話し合いによります。
(1)年休の取得
あなたは、事情があって退職前に60日間休職し、その後に退職を考えているようですが、休職の理由が記されていないため、判断ができかねます。休職は無給扱いなので、年休がたくさんあれば、充当するのが一般的だからです。
年休は、労基法に定める一定の条件を満たした労働者に与えられる権利です。年休の請求権は、原則的には労働者は、いつでも自由に、取得理由を問わず、請求できます。しかし、使用者は時季変更権を持っています。それは、一度に多数の労働者が休暇を取ると、会社の正常な運営ができなくなることがあるためです。使用者は、事業に支障が生じる場合は、年休を他の日に振り返る権利があります。これを時季変更権といいます。
(2)退職の申し出
一般的に、労働者からの申し出によって労働契約を終了することを退職(自己都合退職)といい、使用者からの申し出による労働契約の終了を解雇といいます。
ここでは、労働者からの申し出による退職(自己都合退職)について説明します。
労働者が、ある日突然退職してしまったら、使用者もまた残された同僚も困ってしまいます。そのため、一般的には就業規則などに「退職の申し出は、退職予定日の1カ月前までに申し出ること」というように、あらかじめ後任の手配や事務引き継ぎ期間を見込んで、退職日までの申し出期間を定めておくことが多いようです。退職の申し出をするときには、まず就業規則に退職に関するルールがどのように定められているかを確認し、そのルールに従って、事前に上司と話し合うことが必要です。
なお、退職の申し出に当たっては、契約期間の定めがある労働契約(有期契約)を結んでいた場合とそうでない場合では、ルールが異なるため、注意が必要です。
契約期間の定めがない労働契約(正社員)を結んでいる場合には、就業規則がある場合はその規定に従って、退職届を提出しましょう。就業規則に定めがない場合は、労働者は少なくとも2週間前までに退職を申し出ることによって、いつでも労働契約を解除することができます(民法627条第1項)。この申し出は、原則的には労働者の口頭での意思表示で足りるとされていますが、行き違いのないよう文書で「退職届」などの手続きを踏む方が、無難だといえます。
(3)法的判断と対処策
あなたは、退職日まで休職期間60日、その後年休30日間消化し、退職することを考えているようですが、なぜ、休職期間が必要か納得できる理由の説明がありません。従って、アドバイザーの立場で判断し、回答しますので、ご参考ください。
傷病または疾病などにより、長期療養中の人が休職期間中、年休を請求したときは、年休を労働者が病気欠勤などへの充当が許されることから、このような労働者に対して請求があれば、年休を与えなくてはなりません(行政解釈)。従って、休職が年休の取得を妨げるということはありません。
次に退職に伴う残りの年休を全て消化することですが、あらかじめ退職することが決まっている場合は、年休の残余日数を考慮し、退職届を提出することがベストと考えます。前述したように、使用者には時季変更権がありますが、あらかじめ退職日が決まっている場合には、時季変更権の行使は不可能ですので、問題は生じないでしょう。退職時に未取得年休全日について、一括して年休取得の請求がされた場合、使用者は時季変更権を行使できないので、拒むことはできないからです。しかし、退職する方が、なぜ「自己の都合で休職が必要」かどうかは、問われる問題です。