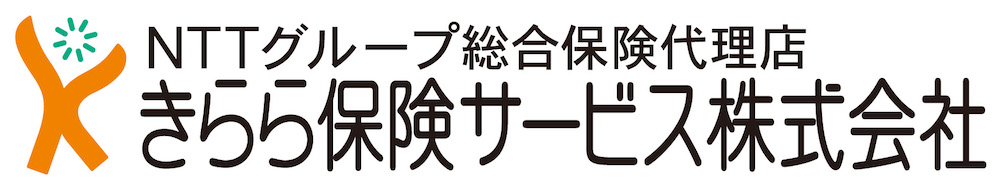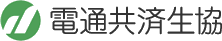Q.1 試用期間中に辞めてくれと言われました
働き出して試用期間1カ月を迎えましたが、「会社の雰囲気に合わないから辞めてくれ」と、突然言われました。このような理由で解雇が認められるのですか?
Answer
ご質問の主旨は試用期間の問題になりますので、試用期間の法的性格などについてアドバイスをさせていただき、その上で、具体的対処策を説明いたします。
(1)試用期間
日本の会社のほとんどが、労働者を採用する場合、本採用にせずに、いったん試用期間を経験させます。 採用試験や面接だけでは労働者の能力、適性を把握しがたいため、入社後の一定期間を試用ないしは見習い期間として現実に就労させ、 その間に労働者を評価して本採用するかどうか決めるという方法です。これは、労働基準法(以下、労基法) でも認められています。
(2)試用期間の法的性格
使用者と試用期間中の労働者との間の契約関係は、期間の定めのない通常の労働契約になりますが、本採用に適しないと判断された場合には解雇し得るように、 解約権が留保された労働契約(留保解約権)とされています。すなわち、当初から労働契約が成立しているものの、試用期間中の労働者の勤務状態などにより、 能力や適格性が判断され、雇用を継続することが適当でないと判断されると解雇または本採用拒否という方法で、解約権が行使されることになります。
(3)留保解約権の行使
留保解約に基づく解雇は、通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められているとされています。しかし、留保解約権の行使は「解約権行使の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上、相当と是認される場合にのみ許される」としています。そこで、試用期間中であることを理由に解雇する場合には、適格性がないという判断の具体的な根拠を示す必要があります。
(4)解雇手続きとの関係について
労基法21条は、「試用期間中の人には、解雇予告制度の適用を除外するとともに、14日を越えて引き続き試用される場合には、解雇予告制度を適用する旨」を定めています。これは、試用期間中の解約の容易性は14日に限定する趣旨だと考えられます。
従って、14日以内に試用期間中の者を解雇する場合、予告は必要なくとも、職業的能力、適性がないこと、もしくは一般の解雇事由があることが必要となります。
以上が試用期間の法的根拠ですが、試用期間中の人の解雇と本採用された人の解雇を比べると、前者はややゆるく、 後者は厳しいといえるでしょう。ちなみに、本採用者を解雇するには就業規則に定められた解雇規定によりますので、 容易に解雇できるのものではありません。試用期間中の人に対しては就業規則の規定によらなくても解雇できますので、 本採用者の解雇ほど、厳しい制約はないといえるでしょう。
(5)法的判断と対処策について
1.法的判断
あなたのケースは、留保解約権の行使に基づく解雇と判断できます。適否のポイントは解雇理由で「会社の雰囲気に合わない」が、「合理的理由が存在し、社会通念上相当と是認される場合」に当たるかです。これまでの判例において、本採用拒否が許容された理由としては、1)剰員、2)誓約書の不提出、3)企業外政治活動に伴う逮捕などによる長期欠勤、4)経歴詐称、5)勤務態度、勤務成績不良などがあげられます。
2. 対処策
そこで具体的対処策ですが、全ての前提は本採用拒否、解雇の理由を明確にすることです。会社の主張する「雰囲気が合わない」では合理的理由にはならないでしょう。
やり方は次の2つです。
1つ目は、社長との話し合いです。
あなた自身の力で社長と話し合い解決するということです。話し合いのポイントは言うまでもなく、解雇の理由についての1点でしょう。継続雇用を希望するなら、被害者意識に立つのではなく、社長の指摘は真摯(しんし)に受け止めた上で、前向きな姿勢で忌憚(きたん)なく話し合うのが、よいでしょう。
職場のトラブルの大半は、コミュニケーション不足にあります。誤解もあると思いますので、気持ちが通じ合えば、評価も一変するかもしれません。雨降って、地固まることを祈念します。
2つ目は、話し合いがつかない場合。
不当解雇で会社と争うというケースです。労働基準監督署や労政事務所に相談するのも一つの方法です。また、具体的に争うとなると、法的判断を要しますので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。弁護士から会社に電話する、内容証明郵便を出す、面接交渉するなどの弁護士による会社との交渉です。交渉で解決しない場合は、裁判になります。
その場合の弁護士ですが、自己解決できれば問題ありませんが、弁護士会や行政で行っている法律相談の活用もあります。会社と争うには、甚大な労力と覚悟が必要です。とはいえ、あなたの気持ち次第ですので、じっくり検討してください。
Q.2 突然の解雇で無一文?
10年も勤務している会社から、ある日突然、「明日から来なくていい」と言われました。会社には退職金制度もなく、会社側はこの件に関してお金を出すつもりはないようです。このまま、無一文で追い出されるしかないのでしょうか?
Answer
(1)問題の所在と、普通解雇なのか整理解雇なのか、退職勧奨か判然としないなど、何が原因であなたが解雇同様の処置をされたのかわかりかねますが、「明日から来なくていい」と発言されたことが解雇の意思表示であれば、解雇には合理的な理由が必要など、厳しい制限があります(労働契約法16条)。
会社には退職金制度がないようですので、通常の退職(自己都合)では退職金は支給されませんが、解雇であれば「解雇予告手当」として賃金の1カ月分は最低保障が義務付けられています(労基法20条)。
あなたは、10年もの長い間勤務し、貢献されたわけであり、相当分の保証を要求することが望ましいように思います。もし、解雇などになった場合には、和解するまで時間を要しますので、争いは求めず、会社都合退職扱いにし、雇用保険の早期に、失業手当金の支払いを受けられるようにしてはいかがですか?
(2)解決方法
しかし、容易に話ができるかどうか疑問ですので、専門的知識のある弁護士に相談することをおすすめします。最寄りの労働相談をできるところをご紹介しますので、そこで詳しく相談され、サポートしてもらってください。
Q.3 リストラに、納得がいきません
「来月いっぱいで」と、リストラ宣言をされました。業界の不況による人員整理とのことでしたが、具体的な説明がなく、納得できません。何か、会社側に一石を投じることはできませんか?
Answer
あなたの怒りは理解しますが、行動を起こすには、人員整理としての解雇が適法に行われたかについて、判断しなければなりません。その根拠からお伝えします。
(1)人員整理(リストラによる解雇)に関する法理
1.解雇とは、使用者の意思で一方的に労働契約を終了させることですが、いつでも自由に行えるというものではありません。しかし、労働契約の終了は、労働者とその家族の唯一の生活源である賃金を失う結果となるため、使用者の恣意的な解約(解雇)は許されず、合理的な理由のない解雇は権利の濫用として無効とされています(労働契約法16条)。 そこで、企業の経営困難などの理由により、人員整理のために行う整理解雇の場合であっても、使用者の自由になし得るわけでなく、経営困難が打開できる対策(不動産を処分する、経営陣の報酬を減らすなど)によって、解雇回避のために努力を尽くさなければなりません。
2. 整理解雇が有効とされる要件(裁判所の判断)
いわゆる整理解雇は、企業経営側の事情による解雇が主です。一般的には、労働者側には責任ないし落ち度がなく行われるもので、会社が整理解雇できるのは、次の4つの条件を全て満たした場合になります。
3. 人員整理の必要性があること
リストラで人件費を削減しないと会社が倒産してしまうなど、会社の存続には、人員整理をするしか方法がないという状況にあることが必要です。
4. 人員削減の回避努力義務を尽くしたこと
まず、配転など社員の犠牲の少ない方法を取ったり、指名解雇を行う前に希望退職者を募るなどの措置を取らなければなりません。
5. 整理解雇の基準・選定に合理性があること
女性や高齢者、あるいは特定の思想を持つ社員などを狙い撃ちにしたような不公平、不平等な解雇は問題外です。
6. 解雇手続に合理性があること 解雇の必要性、時期などについて労働者に十分な説明を行ったり、協議をするなど、労働者を納得させるために真剣な努力がなされたかどうかです。
(2)リストラ解雇の対処策
以上の法理に照らし、不当な解雇に当たれば救済を求めることができます。あなたが解雇撤回を求めて会社と争う(闘う)ということになります。
そこで具体的になりますが、あなたが会社の不当なリストラ解雇に対抗するには、救済機関の助けを求めるしかありません。救済機関とは労働組合、労基署、労政事務所、労働委員会、裁判所などがあります。裁判は弁護士費用の問題が発生しますので、ここでは簡便な労基署と労働組合の活用について、アドバイスします。
1. 労働基準監督署の活用
国の機関である労基署では、会社が労基法に違反しないように取り締まりや指導を行っています。あなたの場合も、労基署に相談するのが最も有効でしょう。労基法違反を申告(104条)することが、あなたの言う会社側に「一石を投じる」決め手となりますが、その是非を含めて、まず専門の職員に相談してください。
2. 労働組合の活用
会社に労働組合があれば労働組合に相談するのが先決です。会社に労働組合がなければ、あなたが労働組合をつくるか、個人加盟ユニオンに加入し、労働組合として会社に対応し解決することです。ユニオンは、労働者の団結の力を背景に、使用者と対等の立場に立ち、働く条件の改善を求めていく、憲法と法律で保障されている権利です。 会社との雇用関係がなくても、会社との労使紛争が残っていれば、その解決に向けて話し合いの場として、ユニオンから団体交渉を求めることができます。
以上ですが、後はあなたの決断だけです。熟慮断行されることを期待します。
Q.4 産休・育児休暇について
就業規定に産休・育児休暇は取れると明記してあるにも関わらず、育児休暇を取って復職したい旨を申し出たところ、「出産を期に区切りをつけたらどうか」と言われました。経営が厳しいため、ぎりぎりまで出社して退職してほしいようなのです。このような場合、会社側に従って退職しなければならないのでしょうか? また、育児休暇を請求したことによって解雇されるのではないかと不安ですし、納得いきません。
Answer
ご相談内容は育児休業の請求と退職勧奨(退職強要)の問題になります。会社との話し合いでは法的根拠が重要になりますので、それらを含めて、対処方法をアドバイスします。
(1)育児休業について
育児休業と介護休業については「育児・介護休業法」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)で定められています。
育児休業制度は、労働者の申し出により、1歳に満たない子を養育するための休業です。最長で、子が生まれた日から1歳に達するまでの間、休業できますが、保育所の入所を希望しているけれども入所できない場合は、子が1歳6カ月に達するまで、育児休業を延長できます。
制度のポイントは次のとおりです。
1. 事業主の義務
事業主は対象となる労働者から育児休業の申し出があったときは、これを拒むことはできません(同法6条1項)。育児休業の権利は、事業主が承認したり、許可することによって行使できる権利ではなく、資格のある労働者が適法な申し出をすることだけで行使できる権利です。事業主は就業規則に育児休業の定めを設けなければなりませんが、定めがなくても取得する権利はあります。
2. 育児休業の申し出
休業の申し出は、休業を開始する日、終了する日など一定の事項を示して、1歳までの育児休業については1カ月前までに、1歳から1歳6カ月までの育児休業については、1歳の誕生日の2週間前までに行う必要があります(6条3項)。
3. 不利益扱いの禁止(平成14年4月1日 改正施行)
事業主は、育児休業の申し出や実際に育児休業を取ったことを理由として解雇のほか、次のような不利益扱な取扱をすることを禁止しています(第10条および指針)。
<不利益な取り扱いの例>
ア.解雇や退職するよう強要すること
イ.自宅待機を命じること
ウ.減給や賞与などで不利益な算定を行うこと
エ.不利な配置転換を行うこと
オ.期間を定めて雇用される人について、契約の更新をしないこと
カ.就業環境を害すること
キ.降格させること
(2)退職勧奨・退職強要
広い意味での退職は、「辞職」=労働者からの一方的解約(使用者の承諾の問題は生じない)と「合意による退職」=自己都合退職、「会社都合退職(使用者の申し出は退職勧奨と呼ばれる)」があります。
退職勧奨の法的性質は、次の通りです。
1.使用者が労働者に対して、合意解約(退職)を申し込んだり、申し込みの誘引をしたりするのが退職勧奨で、社会通念上の限度を超えた勧奨が、退職強要になります。
2.判例では、「退職勧奨そのものは雇用関係にある者に対し、自発的な退職意思の形成をすすめるためになす事実行為であり、場合によっては雇用契約の合意解約の申入れあるいはその誘引という法律行為の性格を併せもつ場合もあるが、いずれの場合も被勧奨者は何らかの拘束なしに自由に意思決定をなしうるのであり、いかなる場合も勧奨行為に応じる義務はない」としています(鳥取地方裁判所 判決 昭和61年12月4日)。
以上が法的根拠になります。
(3)具体的な対処の仕方
前述したように、育児休業法は会社(事業主)にかなり重い義務を負わせています。従って、あなたの育児休業の申し出に対し、会社は、1)絶対に断ることはできませんし、2)出産を期に会社を辞めたらどうかなどと、不利益な扱いをすることは許されません。もし、申し出を断ったときには、罰則はありませんが、56条および57条に基づき、厚生労働大臣、または都道府県労働局長による行政指導を求めることができます。
また、退職勧奨としては、会社の上司の言い方は、会社の経営状況を持ち出して有無を言わせないような態度になっていますが、法律的には単に「退職の合意をしてくれませんか?」という申し入れをあなたにしているだけのことですので、退職の意思がなければ、きっぱり断ればよいのです。
育児休業法は、労働者が家庭生活と職業生活を両立して能力を発揮して雇用を継続し、家族の一員としての役割を円満に果たし、結果として経済や社会の発展に寄与することが目的です。事業主支援と働き続けやすい職場づくりに向けて、ぜひ、あなたが円満な話し合いによる解決を基本に努力され、その先駆けとなってください。
なお、話し合いがこじれるようでしたら、あなたの会社に労働組合があれば労働組合に相談するか、行政の労働相談情報センターの活用が有効ですが、個人加盟ユニオンに加入して労働組合として対応する方法もあります。
Q.5 不当解雇ではないのでしょうか?
就業規則を違反したところ、会社から解雇(契約更新をしない旨)を言い渡されました。違反に関しての始末書も提出していないのですが、これは不当解雇には当たらないのでしょうか?
Answer
ご相談内容は、雇い止めが正当か不当かについてです。
(1)就業規則違反
あなたの説明によると、就業規則に違反したので雇い止め通告を受けたとのことですが、違反の内容について何も触れられていませんので、詳しく説明いただけないと、適切なアドバイスができかねます。始末書を提出する・提出しないの内容ではなく、違反の内容に関わる問題です。
(2)契約更新・解除
あなたは、有期雇用契約(期間の定めのある契約)で採用されているようですので、有期雇用の場合は、不始末を起こした場合や会社になじめないと判断された場合、契約満了時に「契約打ち切りを言い渡すこと」で雇用関係を解除することが可能となります。この場合は、不当解雇には該当せず、「契約解除」雇い止めとなります。
また、契約である以上、期間満了により打ち切られるのが原則ですが、繰り返し更新された場合、期間の定めのない契約と同様と見なされ、正当な解雇理由と解雇手続き(労働契約法16条/労働基準法20条)が必要となります。
(3)雇い止めが不当か解雇権の濫用かの判断と対処策
使用者が、労働者を解雇または雇い止めする場合、「合理的理由」が必要とされています。 あなたの判断で、今回の就業規則に違反した内容が合理的理由に欠け、常識的に考えが不当であると判断されるようでしたら、雇い止め理由を記載された「書面と就業規則」を持参し、最寄りの労働基準監督署に相談することをおすすめします。専門の職員が相談に乗ってくれ、場合によっては会社に対して指導や勧告をしてくれます。
Q.6 派遣会社からの突然の契約打ち切り話で困っています。
登録型の派遣社員ですが、派遣会社から突然契約打ち切りの話をされて、途方にくれています。理由は、積極性が感じられないことと、私用メールとのこと。確かに私用メールは数回しましたが、業務に支障はきたしていません。今後ブランクができてしまったら、契約残存期間の賃金は全額保障してもらえるのか? 派遣会社とうまく交渉できなかった場合、相談する公共機関はどこか教えてください。
Answer
ご相談は労働者派遣契約(派遣元と派遣先で締結)の中途解約の問題になり、原則として、派遣先は雇用契約関係のない派遣労働者を自由に解雇することはできません。派遣先の都合で労働者派遣契約を中途解約する場合には、特別な制限が定められていますので、それらを中心にアドバイスします。
(1)労働者派遣契約の一方的解除(民法541条、543条)
派遣元または派遣先は、原則として、労働者派遣契約を期間途中に一方的に打ち切る(解雇)ことはできません。一方的に解除できるのは、相手方が債務不履行(契約違反)した場合に限られます。たとえば、派遣元の派遣した労働者が労働者派遣契約で定められた仕事をきちんとできない(無断欠勤を繰り返す、派遣先が指示した仕事ができない)など、派遣元に契約違反がある場合には、派遣先は期間満了前に労働者派遣契約を解除できますが、こうした違反がないのに派遣先が自分の都合で一方的に解除した場合には、逆に派遣元が派遣先に対して損害賠償を求めることができます。
(2)派遣先の都合による労働者派遣契約の解除の特別の制限(平成16年厚生労働省告示392号)
1.派遣先がもっぱら自らに起因する事由により、労働者派遣契約を解除する場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって、解除の申し入れをすること。
2.派遣先が派遣労働者に責任がある場合以外の理由(派遣先、または派遣元に関する理由)で解除するときは、派遣元と連携して派遣先の関連会社での就業をあっせんすることなどにより、派遣労働者の新たな就業の機会の確保を図ること。
3.派遣先の責めに帰すべき事由で解除する場合には、派遣労働者の新たな就業の機会を確保し、それができないときには解除の30日前に派遣元に予告するか、または、当該派遣労働者の30日分以上の賃金相当額の賠償を行うとされています。
以上がご相談に関する法理になります。
(3)法的判断と対処策
そこであなたの場合ですが、1つ目は、派遣元が派遣先と結んでいる労働者派遣契約の問題になり、派遣先の一方的解除か都合による解除かの判断が必要で予断は許されませんが、あなたの主張を前提にすれば、派遣先の都合による解除と判断できます。後は特別の制限措置、すなわち、前述2.の(1)~(3)が取られているか否かになりますので、あなた自身で判断してください。
なお、派遣先が契約終了にしたい理由としている「積極性」「私用メール」については、あなたの主張どおりであれば、契約終了の理由としては合理性を欠くもので、判例を踏まえると無理があるといえます(東京地方裁判所 判決 平成15年8月5日)。
2つ目は、派遣元と派遣労働者(あなた)との派遣労働契約(雇用契約)の問題になり、労働者派遣契約が中途解雇されても、あなたと派遣元との雇用契約はそのまま継続しますので、あなたを即座に解雇することはできません。
もし、派遣元がそれまでの派遣先であなたを就労させることができなくなったとしても、雇用契約を結んでいる期間は、派遣元はあなたを雇用者として次の派遣先を提供する義務があります。
派遣元が新たな就業先を提供できなかったことが原因で、あなたが働けなかったときには、派遣元はあなたに賃金を全額支払う義務があります(民法536条)。もし、賃金の支払いについて何らかの争いが生じた場合であっても最低限の補償として派遣元はあなたに休業補償として平均賃金の6割を支払わなければなりません(労基法26条)。いずれにしても、あなたの雇用に責任を持つのは派遣元になりますので、まずは苦情処理担当者とアドバイスした法理を参考にしながら、話し合い、円満解決してください。
相談する公的機関については、各都道府県に設置されている労働相談窓口などが適切と思われます。